京都市の不動産価格が上昇する理由と今後の見通し|需要・観光・投資トレンドを徹底分析

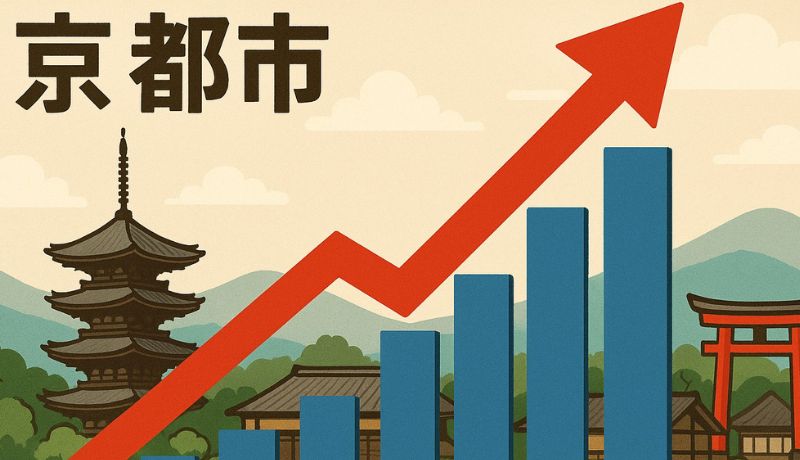
京都市の不動産価格上昇の背景
近年、京都市の不動産価格は全国平均を上回るペースで上昇しています。
とくに 中京区・下京区・東山区 などの中心部では、
コロナ禍以降も価格がほとんど下がらず、
むしろ2024年から再び上昇基調に転じています。
価格上昇の主な5つの原因
① 世界的な観光都市としてのブランド価値
京都市は日本を代表する観光都市であり、世界的に
「京都ブランド」が確立しています。
外国人観光客の回復とともに、民泊・旅館用地の取得
古民家再生への投資
海外資本によるマンション購入などが再び増加。
2024年には訪日外国人がコロナ前水準に回復し、
観光地近接エリア(東山・祇園・嵐山など)の
地価は前年比+6〜9%上昇しました。
② 新築マンション供給の減少と建築コスト高騰
京都市中心部では、新築用地の不足と建築資材の高騰 により、
マンションの供給が極端に減っています。
鉄筋コンクリート価格の上昇
職人不足による人件費上昇
用地取得競争の激化
この結果、新築価格の上昇が中古市場にも波及。
2024年の中古マンション平均価格は前年比+7.5%上昇しました。
③ 古民家・町家の再評価とリノベーション投資
京都特有の「町家」や「古民家」は、かつて老朽化・空き家
問題の象徴でしたが、現在は 観光宿泊・飲食店・ギャラリー転用
による投資対象として再注目されています。
空き家再生補助金(最大200万円)
文化財登録による固定資産税軽減
地元不動産会社とデベロッパーの再生プロジェクト増加
これにより、築50年以上の物件でも立地次第で
高額売買が行われています。
④ 学生・単身需要の安定
京都市は大学が多く、京都大学・同志社大学・立命館大学・
龍谷大学など、学生人口が市内人口の約10%を占めます。
そのため、ワンルーム・1K賃貸需要は景気に左右されにくく、
「安定した賃貸収益が得られる地域」として不動産投資家から
高い人気があります。
⑤ 外国人投資家による高額取引
2023〜2024年にかけて、香港・台湾・シンガポールなどの
投資家による京都市内物件の買い増しが目立ちました。
特に円安(1ドル=150円前後)の影響で、
「日本の不動産が割安に見える」 状況となり、
中心部の高級マンションや旅館用途の土地が買われています。
エリア別に見る価格上昇傾向(2024→2025年)
エリア 2024年上昇率 主な要因
中京区 +8.2% 新築供給減・オフィス需要回復
下京区 +7.6% 観光回復・駅近物件の高騰
東山区 +9.1% 民泊・古民家投資需要
左京区 +5.3% 学生・医療関係者需要
伏見区 +4.5% ファミリー層の郊外移転
京都市全体の地価平均上昇率は+6.8%
(国土交通省・地価公示2025速報値より)
今後の価格推移予想(2025〜2030年)
短期(〜2026年)
観光需要回復・円安継続で、中心部の価格はさらに+3〜5%上昇見込み。
ただし金利上昇リスクにより、住宅ローン需要はやや抑制される可能性。
中期(2027〜2030年)
人口減少が郊外エリアに影響し、伏見・山科は横ばい〜微減。
一方、中心部・観光地近接エリアは高値維持。
「古民家再生」や「観光民泊投資」が市場の主流になる可能性が高い。
京都市での不動産購入・売却のポイント
購入を検討するなら:2025年前半はまだ上昇余地あり。早期検討が得策。
売却を検討するなら:中心部は「今が売り時」。観光・投資需要がピーク。
投資としては:民泊規制を考慮しつつ、「宿泊+飲食複合物件」が狙い目。
周辺環境・生活インフラの発展も価格上昇を後押し
地下鉄烏丸線・東西線の再整備
京都駅南口エリア再開発(ホテル・複合施設建設)
四条通・河原町再開発で商業地価上昇
新たな観光ルート整備(祇園〜清水寺〜伏見稲荷)
これらの開発が進むことで、居住需要と
観光投資需要が同時に拡大しています。
まとめ:京都市の不動産は「ブランド都市」として強い
京都市の不動産価格上昇は一時的なものではなく、
観光・文化資産
外国人投資
学生・定住需要
が複合的に支えている、構造的な上昇です。
2025〜2027年にかけても、中心部を中心に安定上昇が
続く可能性が高い と予想されます。
行動ポイント:
「売却」は今が好機
「購入」は金利上昇前に早めが吉
「投資」は観光・民泊関連エリアを狙う

